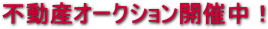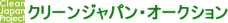2010年12月 27日
大町〜安曇野 田淵記念館と白鳥
”クリスマス寒波”が押し寄せて、日本海側は大雪の荒れ模様だが、
信州の標高1000mの高原も、その1週間まえまでは様相が違った。

土曜日に積もった雪は翌日の晴天にさっさと消え…。
さすがに北アルプスは真っ白だ。長野市からオリンピック道路を抜け、
大町市に至る国道から望んだパノラマ。

前方20kmまでの山を確認できるIPHONEのアプリが、鹿嶋槍、爺ヶ岳、
餓鬼岳などを教えてくれた。
その足元で、誰がこしらえたのか、雪だるまならぬ雪アヒル、見っけ。
ススキの翼もついているが、陽光に溶けてどんどん形を失っていく。

しばらくは北アルプスと一緒。

安曇野・田淵行男記念館に寄り道。駐車場の看板、なぜか登山者用。^^;


日本の山岳写真家の草分けである田淵行男(1905-1989)は、
蝶の研究者でもあった。
館内のライブラリーには、田淵が描いた蝶の彩色画の本も。


カラーフィルムを手に入れることが難しい時代、必要に迫られてのこと
らしいが、緻密さのうちに美しいものへの憧れがこもっている。
大王わさび農場へ1kmという涌水の地。館の外(下というか)には
わさび田が。



犀川の白鳥湖につく頃にはあたりは薄暗くなっていた。
大好きなキンクロハジロが見当たらない。啼き声はすれど。
鴨も白鳥もまだまだ少ない。冬至を過ぎ、年を越して厳寒期に
入らないと、あのかまびすしいほどの光景は見ることができないのだ。
鳥インフルエンザを警戒して、見学者の白鳥への給餌を禁じる看板が
建てられていた。
鹿児島県出水市の状況が、早く収束してくれることを祈っている。

●参加ランキングサイト
応援クリックよろしくおねがいします!
↓ ↓ ↓

 リゾート物件情報Webへ
リゾート物件情報Webへ2010年12月 19日
長崎・荒尾・門司 ほぼ日帰り調査
羽田を発ち、長崎空港に9時10分到着。レンタカーで南下し、長崎市の南端・
野母崎をスタートして雲仙島原経由多比良港へ。
そこからフェリーで長洲に。




長洲から荒尾市に立ち寄り、九州自動車道を北上し門司に到着。
食事をして北九州空港に到着したのが、22時半ごろ。
北九州空港は23時以降に到着する深夜便が多く、空港内も結構にぎやかだ。
出発便は翌日の午前0時50分。空港カウンターは空っぽだった。




午前2時半ごろ羽田に着く便にあまり乗る人はいないと思ったのだが、
6割ほど座席は埋まっていた。高齢者や会社員の姿はあまり見かけないが、
若い人が多く外国人の姿もちらほら。
制服はまちまちだが、威勢のいいツアコンみたいなお姉さん客室乗務員が
4人ほど、一言の無駄も無いほど手際よくお客を誘導していた。

●参加ランキングサイト
応援クリックよろしくおねがいします!
↓ ↓ ↓

 リゾート物件情報Webへ
リゾート物件情報Webへ2010年12月 08日
私事ですが…
今、とても残念なことがある。
コーヒー豆を頼んでいた焙煎の店が営業に終止符を打ってしまったのだ。

オープンして8年。店の存在に気づいたのはその2、3年後で、以来、
ほとんど頼りっきり。
自宅からふた駅と遠くないのに、忙しさにかまけて、メール便で送って
もらっていた。
30代半ばぐらいの夫婦が営むその店に、何度か足を運んだことがある。
重労働ともいえる焙煎の合間に、ご主人が淹れてくれたコーヒーの
美味しさは忘れられない。
丁寧に選ばれた品質のよい豆と適切な焙煎によって、どんなふうに淹れても、
さわやかに澄みきったコーヒーが仕上った。
先月、いつものように注文しようとホームページを開いたら、月末に閉店
との文字が…。
焙煎したての豆の美味しさをわかってほしいと、100グラムずつの注文にも
応じてくれたり、全国発送に加えて、近所にはみずから配達もする
きめ細かなサービスだった。
手間ばかりかかって、収益が生まれなかったのだろうか?
最後になってしまったコーヒーを大切に味わっているところだが、
豆はあと10日ほどで底をつく。
新たな店を見つけようとネットを探して、コーヒー豆の全国発送をする店が
数多くあることに驚いた。
業界の競争は相当に激しいようだ。
これから、どこに頼めばよいのやら。
コーヒーに関しては、胸の中にぽっかり、穴が空いたような気分である。
●参加ランキングサイト
応援クリックよろしくおねがいします!
↓ ↓ ↓

 リゾート物件情報Webへ
リゾート物件情報Webへ2010年11月 25日
姫路港⇔小豆島 フェリーで往復
朝7時前・品川発の新幹線で姫路に。
姫路港までバスを使い、港から小豆島の福田港行きフェリーに乗る。
すでに沢山のバスや乗用車が待っていた。


港への到着予定は午後1時。

船内は、ひろびろとして綺麗だった。観光客で、結構混み合っている。


物件調査をしたらすぐにUターンしないと、その日のうちに東京に戻れない。

とんぼ返りで福田港を出ると、航路の途中で、辺りが暗闇になった。
●参加ランキングサイト
応援クリックよろしくおねがいします!
↓ ↓ ↓

 リゾート物件情報Webへ
リゾート物件情報Webへ2010年11月 24日
古民家好き必見! 川崎市・日本民家園
神奈川県川崎市北部・生田緑地と呼ばれる丘陵地帯に、江戸時代の
民家を集めた「日本民家園」がある。


1967年に開館した野外博物館で、信越、東北、関東の民家から信州の
水車小屋、沖永良部の高倉、三重県志摩の歌舞伎舞台まで25軒が移築・
展示されている。※18件は国や県の重要文化財に指定。


» 続きを読む
●参加ランキングサイト
応援クリックよろしくおねがいします!
↓ ↓ ↓

 リゾート物件情報Webへ
リゾート物件情報Webへ2010年11月 23日
上田市 ともし火博物館
このところ上田方面に出かけることが多いのだが、この「ともしび博物館」は
通り過ぎるだけだった。

ちょっと時間が空いたので立ち寄ってみたが、なかなか立派な施設だ。

入り口で、写真を撮っていいかと聞いたら、目的を聞かれ、営業目的だと
断られるので、趣味で、と応えたら、お断りします、と言われてしまった。
そこで、「リゾート物件情報」の取材です、と応え直したら、それなら結構です、
と。
館内にはランプや行灯、蝋燭などが展示されている。


ともし火に因む浮世絵、蝋燭やガス灯


行灯


もあり、解説の映画が上映されていた。
外には立派な庭園や茶室もあった。


館はひろびろとした公園に囲まれたエリアにあり、一見の価値はある。

●参加ランキングサイト
応援クリックよろしくおねがいします!
↓ ↓ ↓

 リゾート物件情報Webへ
リゾート物件情報Webへ2010年11月 17日
長野県上田市 美ヶ原に寄ってみた
上田市武石の「美しの国」の帰りに、足を伸ばして美ヶ原に上ることにした。


標高2000mのこの高原には、もう40年以上前の高校生の時に来たはずだ。

日常を離れて触れる草原や白樺といった美しい自然への感動、当時さわやか
だった、口もきけなかったクラスメイトへの思いに包まれ、来たような気がする。


今は、遊園地のような美術館が頂上を占めていて、昔の思い出が甦ってこない。

広い草原や高原から見下ろす周囲の山々が、かすかに美ヶ原の面影を残す
だけで、すっかり観光化されてしまった。

もう昔のようには戻らないのだと、白樺湖方面に抜けて帰るのを諦め、
元の道を引き返した。

●参加ランキングサイト
応援クリックよろしくおねがいします!
↓ ↓ ↓

 リゾート物件情報Webへ
リゾート物件情報Webへ2010年11月 10日
長野県 佐久のイルミネーション点灯式
2年ほど前に見た佐久市のイルミネーションは、とても綺麗だった。
今日はたまたまその点灯式だというので、樫山工業の駐車場に車を停めて、
見に行った。

大勢の人が見に来ており、報道の人は壇上に上がって撮影している。
こちらも壇上に上がって撮影することにした。
主催者よりやや貫禄が落ちる佐久市長も来ていて、いっせいに点灯。


景気も回復したので、今年は白雪姫から、シンデレラに代えて気張った、
という主催者の説明があった。

長い敷地をふんだんに使ったイルミネーションは、来年の2月まで
点灯されるそうだ。


●参加ランキングサイト
応援クリックよろしくおねがいします!
↓ ↓ ↓

 リゾート物件情報Webへ
リゾート物件情報Webへ2010年11月 05日
早朝の琵琶湖 漕艇場と石山寺
早朝6時でも琵琶湖畔では、釣りする人やカヌーを練習する人がいる。
湖を見ていると、昔歌った琵琶湖周航の歌が自然と出てきた。
♪われは湖(うみ)の子 さすらいの
旅にしあれば しみじみと
のぼる狭霧(さぎり)や さざなみの
滋賀の都よ いざさらば


石山の駅から石山寺に向かった。

ここは、紫式部が源氏物語を書いたところとして有名だ。
行ってみるととても大きなお寺だ。

参道をしばらく行くと、料金所があって、
本堂や金色堂などは、料金を払わないとみることはできない。

時間が無いので、引き返してバスで駅に向かうことにした。
バス停の前は、琵琶湖から流れる川になっていて、
ここでもカヌーを漕艇している。

●参加ランキングサイト
応援クリックよろしくおねがいします!
↓ ↓ ↓

 リゾート物件情報Webへ
リゾート物件情報Webへ2010年11月 02日
新潟県上越市
道の駅「うみてらす名立」の風車
新潟県上越市は、城下町の高田や港町の直江津など、さまざまな要素が
混ざり合う魅力的なまちだ。
「季刊・リゾート物件情報」の取材が終わると、ちょうどお昼どき。
日本海へ出て、名立にある道の駅「うみてらす名立」へ足を運んだ。
レストランや直売所だけでなく、日帰り温泉とホテルも備える。

平日ながら、駐車場は車であふれていた。
海鮮丼は、2階のレストランの看板メニュー。味噌汁と香の物つき。
ネタの新鮮さはいうまでもなく、なかなかのヴォリューム。ご飯もしっとり、
ツヤツヤ。


1階の直売所では、海産物はもちろん、野菜、季節のきのこも販売。

女カニとはズワイガニの雌。蟹はシーズンまでまだ時間があるためか(訪問は
10月上旬)、ロシア産の数量が勝っていた。
石鯛もお買い得。


この日は最高気温が25度と高く、カメラのレンズが曇る曇る…。
海側から見た外観。

日本海に沈む夕日の眺めが圧巻と聞いたが、海の眺望は併設のホテルに
占められ、レストランから海は望めないのは残念。
荒天の際は波をかぶりそうなほど海とまぢかに対峙する館の運営は、
旅行者が考えるほど簡単ではなさそうだけど。
浜へ出ると、施設の横に、風力発電の風車が一基、かすかな金属音を立てて
回っていた。

風車、2008年5月の日記 「黒姫の別荘族・御用達 新潟県上越市 「魚勢」」
でも登場したっけ。
その後、冬の落雷被害によって稼動休止に追い込まれるなどで、2009年度
時点の累積赤字は約1億5600万円に上る、と先ごろ新聞紙上で取り上げられて
いた。
健康被害を訴えるひとが出るなど、そこに暮らすひとびとが対立する東伊豆町
のようなトラブルが出ることなく、冬の日本海にも耐える頑丈なマシンが、充分な
量を安全に発電してくれるなら、言うことないのに。
改善の余地、大アリだ。
現在のところ、クリーンエネルギーの代表格と目される風力発電。
この先が気になります…。
●参加ランキングサイト
応援クリックよろしくおねがいします!
↓ ↓ ↓

 リゾート物件情報Webへ
リゾート物件情報Webへ